うちの生徒_澄原 夕海
夕海が机の上に浅く腰掛けた。こちらに向かって両脚を広げる格好になると、白く細い脛が夕焼け色に染まっていく。スカートはほとんど捲れてしまい、ストライプのショーツが透けて見える。
「来て」
彼女の声に導かれ、机の前に膝をつく。ショーツの縁に沿って指を這わせると、すでにしっとりと濡れていた。布地越しでも分かるほどの湿り気が指先を包む。鼻腔に甘酸っぱい匂いが入り込んでくる。それは彼女の汗と花のような香りが混ざった、独特の臭いだった。
ズボンを下げると夕海が息を呑むのが分かった。硬く膨張したものに彼女の膝裏が触れただけで体が跳ねる。そのまま腿の間に挟ませた。ヌメヌメした愛液が茎全体を包み込み、熱が一気に上がってくる。
「んぁっ!? あっ……あぅ……」
彼女が喉の奥で呻き声を押し殺す。僕は腰を前後に揺らしながら腿の隙間へ出入りさせた。ぐちゅ、ぬちゅ……と粘着質な水音が教室内に響く。汗と淫液が混ざり合い、濃厚な蒸気が漂った。
「だめ……これぇ……すごいっ……」
夕海の背中が反り返る。机がギシギシ軋む音と、互いの荒い呼吸が合わさって淫靡な交響曲となった。
机の上で四つん這いになった彼女は、自らスカートを捲り上げて秘所を見せつけた。指で割れ目を左右に開くと桃色の粘膜が露出し、そこから透明な汁が糸を引いて滴り落ちる。甘ったるい匂いが空間を支配していた。
「舐めていい?」
彼女が顔を伏せて僕のモノを咥えようとしたとき、目の端で何かが煌めいた。窓ガラスに反射して映る二人の姿──制服の裾が乱れ、下半身を絡ませ合う少女と男。倒錯的な情景に全身が粟立つ。
唾液まみれの舌が鈴口を割り、ちゅぱっという卑猥な音と共に亀頭全体が飲み込まれていく。口腔内の熱い粘膜と舌使いに翻弄されながらも、理性は最後の線を守ろうとしていた。
「お、おれ……もう出そうっ……」
彼女が頭を引き抜こうとした刹那──
「出して」
搾り出すような囁き。次の瞬間、頬肉が竿を根元まで強烈に締め上げてきた。
どぴゅっ!びゅるるるっ!
「んんっ……んんぅう……!」
喉の奥で精液を受け止めながら彼女の頬が膨らむ。溢れ出した白濁液が唇の端から垂れ落ちて机に飛沫を撒いた。ゼリー状の塊が彼女の喉に流し込まれていく様子が目に焼き付く。
夕海の口から引き抜いた瞬間、まだ弾むように脈打ち続けるものを彼女の顔に向けて突き出す。
「……いいの?」
涙目で上目遣いをする彼女に向かって何度もうなずいた。最後の一滴を振り絞るように腰を振ると、白く濁った液体が弧を描いて彼女の顔面に飛び散った。
びちゃっ!べちょぉっ……
「んくぅっ……熱いぃ……!」
額や頬骨にべっとりと付着した精液は夕暮れの光を反射して艶めかしく輝く。睫毛に掛かった液滴がゆっくりと流れ落ちていき、彼女の唇へと辿り着いた。夕海はそれを舌で掬い取ると、
「甘い……けど、生臭い……」
恍惚とした表情で呟いた――
呪文
入力なし




















































































































































































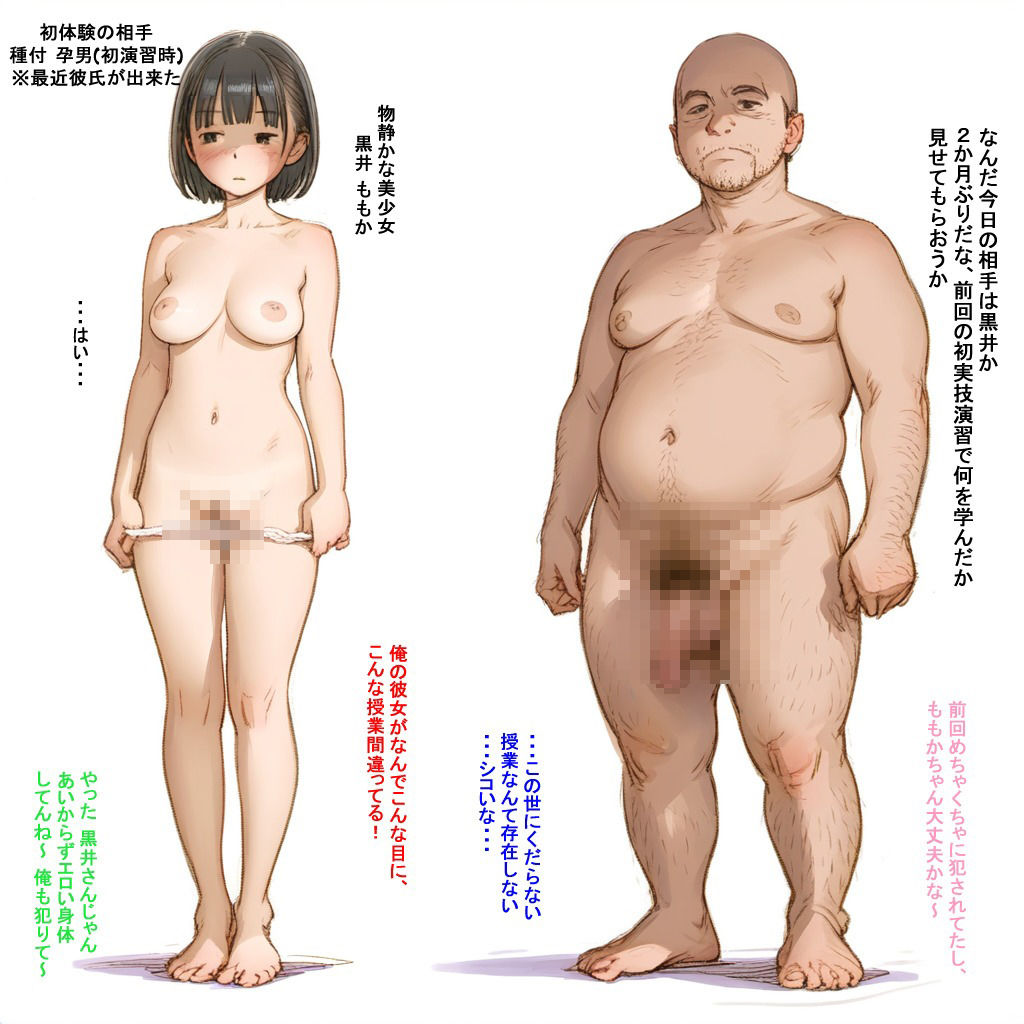

















![[11枚] 「40世紀ともなるとクローンで子孫が作れるのでパートナーにアンドロイドを選ぶ人も多いわ。特に人気なのはロリタイプってわけ。あなたもいかが?イクぅううう♥」(ロリっ子大集合・大人向け506)](https://chichi-pui.akamaized.net/uploads/post_images/originals/775d19b4-62b5-496a-9a25-a4859ae94c8e/dd21f1e3-3b0e-491d-a5fb-ce379c7eadb3.png?impolicy=thumbnail&w=400&h=400&x=512&y=0)






















































































