良妻賢母の堕ちた先
今日も、いつもと変わらない日常が、私を包み込んでいた。
しかし、その平穏は、ある日突然、崩れ去ることになる。
「良夫君のお母さん、ちょっと話があるんです。」
息子の友達、隆司が突然訪ねてきた。まだ少年らしい面影を残す彼は、でも、その瞳に不思議な光を宿していた。私は、息子の友達ということもあり、特に警戒せずに応対した。
「どうしたの、隆司くん?何かあったの?」
彼の言葉を待つ間、私は彼の目をしっかりと見つめた。
その瞳の奥に、何か熱いものが渦巻いているのを感じて、少しドキッとした。
「実は……僕、千里さんが好きなんです。付き合ってください!」
えっ、今なんて? 息子の友達からこんな言葉をかけられるなんて、全く予想外だった。思わず笑ってしまったけど、隆司の目は真剣そのもの。
「隆司くん、そんなこと言っても……私はもうおばさんだし、あなたはまだ子供でしょ?」
そう言って、私は彼の手を優しく払いのけた。
でも、隆司は引かなかった。彼は私の目を真っすぐに見つめ、真剣な表情で言った。
「僕は本気です。千里さんが好きでたまらないんです。」
その瞬間、隆司は私の胸に手を伸ばした。突然の行動に、私は驚いて平手打ちを食らわせた。
「何するの!隆司くん、もう帰って!」
私は隆司をドアの向こうに押し返し、バタンとドアを閉じた。
「ふー、なんなのあの子…突然、こんな私に…」
ドアの内側で、私の胸は高鳴っていた。
その鼓動は、しばらくおさまらなかった。
ーーーー
「ただいまー!」
息子の明るい声が、私の官能的な思考を断ち切った。
私は深呼吸をし、母としての顔に戻る。夕食の支度、宿題の確認、お風呂の準備……日常のルーティンが、私の心を穏やかに整えていく。
あの子のことは、まるで夢だったかのように、その日のうちに忘れ去られていった。
夜、ひとりシャワーを浴びているとき、私はふと昼間の出来事を思い出した。
隆司くんの真剣な眼差し、突然の告白、そしてあの危うい雰囲気。
(本気?あの眼差し、まさか……少年の初々しい憧れよね……。)
「ま、おばさんの私にそんなことないよね。」
私は軽くつぶやき、シャワーの音に声を飲み込ませた。
でも、話はそれで終わりではなかった。
まだ、私は、そのことにまだ気づいていなかった
呪文
入力なし


























































































































































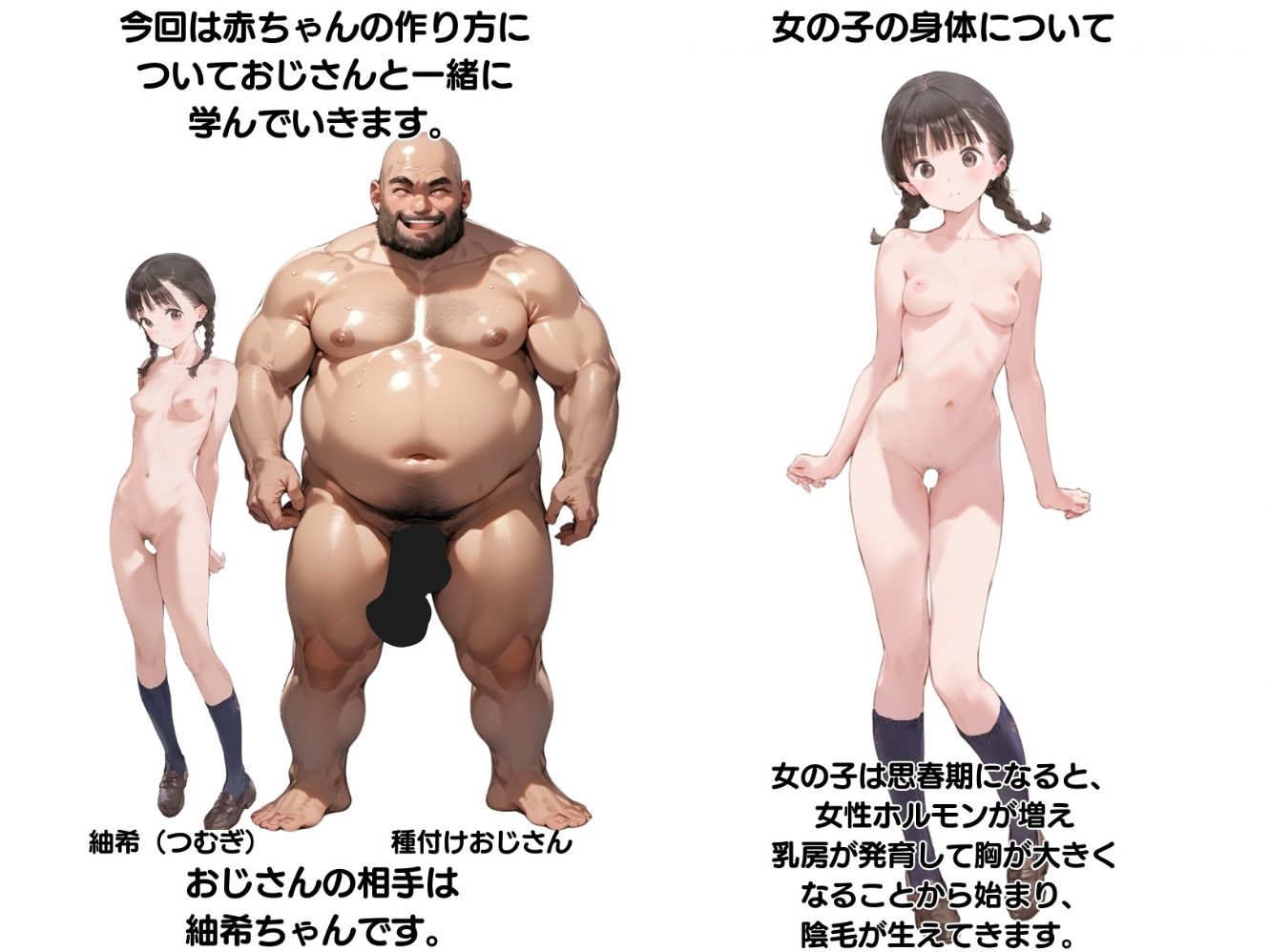






![[3枚]【企画・5分で用意した画像】5分で用意したエロリエロ画像(ロリっ子大集合・大人向け504の3)](https://chichi-pui.akamaized.net/uploads/post_images/originals/0ca4a6b7-d084-4bae-b1f4-44e4863d338a/72429c5b-aa7c-4c95-97bd-2ba7367305dc.png?impolicy=thumbnail&w=400&h=400&x=512&y=0)

































































































